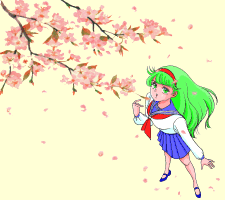銀河戦記/波動編 第二章 Ⅴ ストリートギャング
第二章

↑ Microsoft Edge image Creator AI生成
V ストリートギャング
およそ二十年ほど時を遡り、アントニーノ・アーデッジの少年時代。
とある街角、ゴミが散乱しビルの壁には落書きがされており、路上には薬中毒の男女が暗い表情で徘徊している、まさにスラム街のような風景だった。
その一角の廃ビルの地下室にたむろしている少年達がいた。
各自それぞれ手持ちの拳銃や自動小銃の手入れをしている。
そこへ扉が開いて、一人の少女が入ってくる。
「もうじき来るよ! トニー」
彼女は見張り役のルイーザ・スティヴァレッティ。
トニーと呼ばれたのは、リーダーのアントニーノ・アッデージ少年だ。
「よし! 行くぞ!」
サブマシンガンを肩に担いで立ち上がるトニー。
部屋を出て、入口の前に止めてあった車に乗り込む少年達。
「出発する!」
全員が乗り込んだところで、運転席のフィロメーノ・ルッソロが車を発車させる。
少し走った所、とあるビルの裏口で車を停車させた。
「配置につけ!」
トニーが指示を出す。
「分かったわ」
「了解」
ルイーザともう一人、エルネスト・マルキオンニが車を降りて路地裏に入った。
残った者は、頭を低くして車内に隠れるようにうずくまる。
やがて一台の車がビルの裏口へと入ってきた。
「来たぞ!」
と同時にルイーザが裏口から飛び出し、エルネストが後を追いかける。
「きゃあ! 助けてー!」
車の前を塞ぐように立ち止まるルイーザ。
「逃げるんじゃない!」
抱きつくエルネスト。
目の前で繰り広げられる暴漢現場だが、車に乗った運転手はドアを開けずに、無線でどこかに連絡しているようだった。
当然の行動だろう。
その車は防弾仕様の現金輸送車である。
何があってもドアを開けたり降りたりしてはいけない。
「しようがねえなあ」
そういうと、サブマシンガンを構えるトニー。
それを見て驚いた表情を見せる運転手。
「やっちゃえ!」
ルイーザが囃し立てる。
「ちょっと離れてろ!」
と皆に注意してから、ドアの錠あたりに弾を撃ち込んだ。
一発の跳弾がトニーの右頬をかすめ通るが、ピクリともせずにカッと目を見開いたかと思うと、ドアを強く蹴飛ばした。
反動でドアが弾けるように開く。
すかさずエルネストが銃を突き付けて、
「降りるんだ!」
と運転手に促す。
しぶしぶ車を降りる運転手。
その瞬間、背後から拳銃の銃底で殴り倒された。
「鍵は?」
車内のダッシュボードのあたりを見回す。
「こいつが持っているよ」
ルイーザが、運転手の腰ベルトに鍵の束が吊り下げられているのを発見した。
その鍵束を奪って、車のサイドドアの鍵を開ける。
と突然、中から発砲される。
しかし事前に察知していたトニーは、狙いを澄まして反撃して相手を倒した。
「殺したの?」
ルイーザが心配そうに尋ねる。
強盗はしても殺人はしないのがチームの鉄則としていた。
「いや、急所は外している。肩口を撃っただけだ」
「よかった」
「さあ、手っ取り早く片付けようぜ」
現金の詰まったジュラルミンケースを運び出して、乗ってきた車に移し替える少年達。
「しかしなんで金庫を積まずにボディーガードを乗せてんだろうな」
本来なら現金輸送車には堅牢重厚な金庫を搭載し、車ごと奪われないようにエンジンの非常停止装置が組み込まれているのだが。
「知るかよ。経費削減じゃないのか?」
そうなのだ。
強盗計画も、金庫を積んでいないことを確認していての犯行だったのだ。
「よし、積み終わったぞ。ずらかるぞ!」
全員、車に乗り込んで現場から立ち去った。
アジトに戻った少年達。
「いくらくらいあるの?」
開いたジュラルミンケースの中の現金を見つめながら、目を輝かせてルイーザが尋ねた。
「そうだな。ざっと十三億ってところかな」
トニーが答える。
「それでこれからどうするんだ? 今頃警察が必死になって捜しまわっているぞ」
エルネストが心配そうな顔をしている。
「いいかげんこの街にいるのは危険だ」
「高跳びか?」
「以前から話していたが、この惑星を離れることにする」
「どうやって? 俺達顔バレしているから、空港に行けば捕まるのは必至だぜ」
「輸送船に紛れ込んで脱出する」
「上手くいくかな?」
「逃がし屋に頼むことにする。一億ほど金を掴ませればやってくれる」
「一億?」
「妥当な金額だよ。奴らだって、俺達が強盗で金を奪ったくらいの情報は得ているはずだからな」
「分かった。残りの金はどうする? 現ナマを持ち運ぶのはヤバいからな」
「闇商人に会って、宝石に換えてもらうさ」
「それなら、ポケットに入れて運べるな」
「いいわね。Go ahead よ」
少年達は意見が一致して、密航による惑星脱出が決まった。
惑星脱出行だったが、まさか乗り込んだ輸送船が海賊に襲われるとは夢にも思わなかったのだ。
↓ 1日1回、クリックして頂ければ励みになります(*^^)v
ファンタジー・SF小説ランキング

11
銀河戦記/波動編 第二章 Ⅳ 海賊基地
第二章
Ⅳ 海賊基地
ルイーザ・スティヴァレッティの案内で、基地内の施設を見て回る少年達。
それぞれ気に入った施設があったようだ。
体育会系でいつも腹ペコなブルーノ・ホーケンは食堂。
料理が得意なジミー・フェネリーは、そこの厨房。
ゲーム好きのエヴァン・ケインは、ゲームセンターのある娯楽場。
機械好きのフレッド・ハミルトンは、機関部が部外者立入禁止なので劇場。
乗り物好きのマイケル・オヴェットは、歴代宇宙船が飾られている博物館。
一同の総意として、無法者が集う海賊基地において福利厚生施設が充実している事が驚きの対象だった。
そしてアレックスの感心した事は、ギルドだった。
ギルドとは、民間銀行と人材斡旋、そしてクエスト依頼を請け負っている。
民間銀行は金融機関であり、個人などの資産管理を扱っており、クレジットカードも発行して基地内ではどこでも使用でき、貨幣を持ち歩く必要がない。
人材斡旋は、クルーが不足している船に各種職種の船乗りを斡旋している機関である。
そしてクエスト依頼とは、商船襲撃の他に、
「他国に捕らえられている海賊仲間を救出するために収容所惑星を襲撃する」
「銀河中心ブラックホール周辺にある未踏宙域かつ危険地帯にある惑星の発見」
などの毛色の違うものが挙げられている。その中でも、
「ロストシップの情報求む」
というクエストが最も報酬が高い。
「それじゃ、船に戻りましょうか」
一通りの見学を終わりにして、途中食堂で腹ごしらえしてから、船に引き返す一行。
「それにしても、海賊基地というから極悪人のたまり場かと思ってました」
エヴァンが感心していた。
「びっくりした?」
「はい」
「まあ、ここのボスができた人ですからね。生殺与奪は好まず、一般人の乗船する旅客船は襲わず、商船や富豪の自家用船を狙っているわ」
「そうなんですか」
船に戻ってくると、物資の搬入中であった。
「おお、丁度いいところに戻ってきたな。手伝ってくれ」
モレノ・ジョルダーノ甲板長が、少年達を見つけて声を掛けた。
「分かりました。みんな、手伝おう!」
アレックスが声を掛けると、
「よっしゃー! いっちょ力のあるところを見せてやるよ」
体力自慢のブルーノが答える。
「わかったよ!」
他のものも賛同して手伝いを始めた。
「姉さんは、どうしますか?」
先輩であるルイーザに尋ねるモレノ。
ルイーザはレーダー手なので、一応手は空いているはずだからだ。
「いや、あたしはひと眠りするよ。子供の相手で疲れたからね」
「そりゃどうも。お休みなさいまし」
会釈するモレノ。
「じゃ、そういうことで」
右手を軽く上げて、乗船口から船内へと入ってくルイーザだった。

船橋にルイーザが戻ってきた。
その顔を見るなり、アッデージ船長が言う。
「ご苦労様。彼らはいい子にしていたかな?」
「そうね。皆、素直でしっかりした子だったわ。仲間にして正解だったと思う」
「君もそう思うか……」
「将来が楽しみだわ」
「そうだな」
「それじゃ、しばらく休ませてもらうわ」
「おお、お休み」
手を振って船橋を出てゆくルイーザ。
この二人の付き合いは長く、アッデージがストリートギャングとして暴れていた頃からの仲間で、互いに気心の知れた仲である。
フィオレンツォ・リナルディ副長が近寄ってくる。
「補給が済みました」
「そうか」
「それから、親父が呼んでます」
「親父が? 分かった、すぐに行こう。後を頼む」
「分かりました」
副長を残して、船橋を退室するアッデージ船長。
↓ 1日1回、クリックして頂ければ励みになります(*^^)v
ファンタジー・SF小説ランキング

11
銀河戦記/波動編 第二章 Ⅲ 帰還
第二章

↑ Microsoft Edge image Creator AI生成
Ⅲ 帰還
獲物を無事に頂いてホクホク顔の海賊達も、そろそろ休息が必要だ。
「進路をガベロットへ取れ!」
海賊基地ガベロットは、国際中立地帯のどこかに密かに建設された要塞である。
数多くの海賊達が集まる悪の組織の中枢である。
燃料・食料補給と船の修理・整備の他、海賊達の休息する簡易宿舎や娯楽設備などが整っている。映画館もあれば病院もある至れり尽くせりの基地である。
それらはすべて、海賊達が治める上納金で成り立っているのだが。
いわば一つの国家としての体をなしているので、上納金もいわば税金みたいなものであろう。
海賊基地に近づく海賊船フォルミダビーレ号。
その海賊基地はあまりにも巨大で、一つの惑星ほどにも思えるが、銀河恒星地図にも掲載されていない秘密の基地である。いざとなれば移動も可能な機動要塞でもあった。
「こちら、フォルミダビーレ。入港許可願います」
レンツォ・ブランド通信士が、基地との連絡を取っている。
『こちらガベロット、貴船の入港を許可する。十二番デッキより進入せよ』
「了解。十二番デッキより入港します」
ブランドが応答すると、フィロメーノ・ルッソロ操舵手がアッデージ船長を見つめる。
「入港せよ……ちょっと待て」
指示を一旦中断してから、副操縦士となっているマイケル・オヴェットを指名する。
「マイケル。君が操舵して入港してみろ」
意外にも入港という重大時を見習いにやらせようというのだから、船内の他のオペレーターも驚くだろう。
「僕がですか?」
最も一番驚いたのはマイケルだ。
「男は度胸だ、根性で操舵してみろ。多少は船に損傷を負っても構わんぞ」
「多少は……ですか?」
「ははは、いいからやってみな」
ルッソロも肩を叩いて、操舵コントロールシステムを彼に預けた。
「だ、大丈夫かなあ……」
「操舵説明書は隅々まで読破して熟知したんだろ?」
「はい、何とか……」
恐る恐る操舵装置に手を掛けるマイケル。
「なら心配するな、君にならできる。どんと行け!」
「分かりました。やってみます」
操舵輪を持つ手に力が入る。
「入港シークエンスシステム作動します」
入港に関する自動装置を起動させるマイケル。
船のコース取りから制動逆噴射タイミング、着岸・船台ロックまでの一連の手順を自動で行うシステムである。
自動とは言ってもある程度の微調整が必要なので、マニュアル操作も必要である。
二十分後、緊張とスリル手に汗握りながらも、船を無事に着岸させることに成功した。
「よくやったぞ、大したものだ」
ルッソロがポンと肩を叩いて称賛した。
「冷や汗ものでした」
大きくため息をつきながら、緊張から解放されて胸をなでおろすマイケルだった。
「やればできると言ったとおりだ。合格だ!」
アッデージ船長もべた褒めした。
「ありがとうございます」
マイケルがお礼を言うと、
「ご褒美に半舷上陸を許す。誰か、基地の案内をしてやれ」
と、上陸許可を与える船長だった。
「あたしが案内するよ」
名乗り出たのは、レーダー手のルイーザ・スティヴァレッティ。
「おい。少年を部屋に連れ込むなよ」
誰かが嘲笑する。
「失礼ね。あたしだって選ぶ権利はあるよ。ガキには興味はない!」
「そうだったね。ロマンスグレーのおじさまだったよね」
「言ってろよ!」
船内では唯一の女性なので、何かと冷やかしされるのだが、これでも海賊の一員なのでヤワではない。
「おい。ついでだから、他の五人も連れて行ってくれ」
船長が追加要求する。
「あたしは、保育園の引率かよ?」
「ついでだ」
「しょうがねえな、分かったよ。ガキ共を呼んでおくれ」
「分かった。乗船口に集合させておくよ」
数時間後、少年達を連れて船を降りるルイーザ。
「いいかい。勝手に歩き回るなよ」
「はーい」
元気に手を上げるエヴァン・ケイン。
彼が、海賊達から一番可愛がれているので、一切気後れもしないようだ。
ふと横の方を見ると、荷物搬入口から、両手を縄で縛られた少年達が降りてくるのが見えた。どうやら、入港している奴隷商人の船へと連れ出されるところのようだ。
「彼らはどうなるんですか?」
マイケルが質問する。
「見ての通り、奴隷商人に売られたんだよ。どこぞの貴族か富豪の館で一生奴隷として働かせられるのさ」
「何とかならないのですか?」
アレックスも気を揉んでいるようだ。
「飯食って、寝て、甲板掃除するしか能のない奴にはお似合いさ」
「ですが……」
「君たちは、飛行艇を奪って脱走を図るという行動力を見せてくれたから仲間に取り入れられた。しかし、彼らのように努力もせず、現状を打開しようとする根性のない者は、この海賊船では無用ものだ」
向こう側も気づいたらしく、立ち止まってアレックス達に視線を送るが、
「こら、立ち止まるな! さっさと歩け!」
奴隷商人に強い口調で促されて、弱弱しく歩き出す。
一緒に遊んだ仲間が奴隷商人に売られていくのを、ただ見守るだけしかできない自分達を情けなく思うアレックス達だった。
↓ 1日1回、クリックして頂ければ励みになります(*^^)v
ファンタジー・SF小説ランキング

11